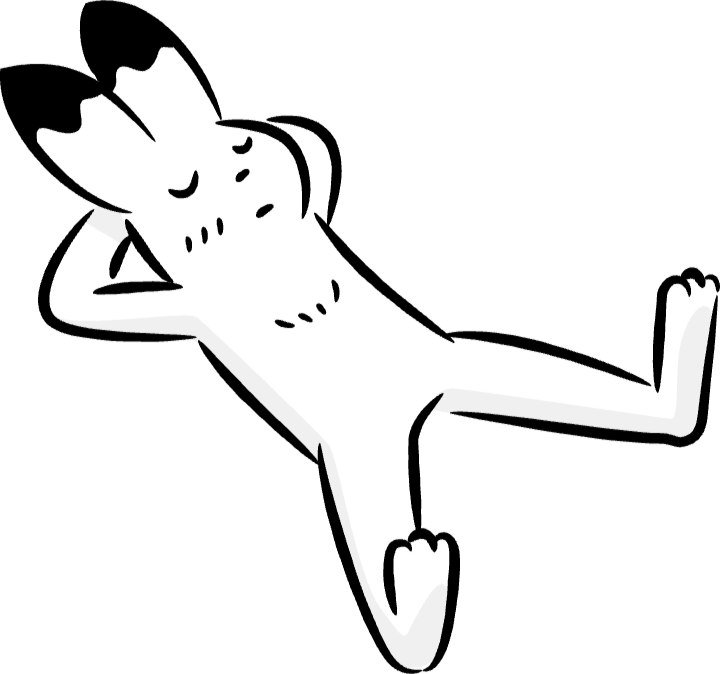社会人という語が凝縮する闇
私たちは普段からさして意識することなく「社会人」というきわめて奇妙というほかない言葉を使っている。あるいは「社会に出る」というような表現。よくよく考えてみると、おかしな言い方である。英語などにも翻訳できない。そもそも「社会」とは何か? これは本当に英語でいうところの「society」なのだろうか。
たしかに「社会」という語は「society」という語を翻訳するために19世紀末に生みだされた。ここではさらに「会社」という言い方もまた「society」の訳として使われていたということを思いおこしてみてもいい。
というのも、まさに日本においては「社会」と「会社」という二つの異なる概念が、現代においてもあまりにも密接に重なりあうことがある。社会のために生きるということが、会社のために生きるということとしばし同一されてしまう。これは公共性を支える「公」、つまり「おおやけ=大きな家」の概念に関しても言えることなのだろうけれど、近現代の日本の知の枠組みにおいては、社会や会社というものがとかく「家」のようなものとして理解されてしまうのだ。さらには「国」でさえ「国家」として理解されている。
きっとこのような発想の枠組みのなかに置かれているものの一つが「社会人」であるのだろう。すくなくとも現代の日本においては「社会人」という一人前の存在として認められるためには、会社などに勤めていなければならないとしばしば考えられているようだ。たとえば、生活保護の受給者が社会人と呼ばれることはあまりないのではないだろうか。
しかし、ごく当たり前の話をすれば、社会というものは、本当は普段から私たちが想像する以上に、広い。会社の外にも社会はある。家のなかにも社会はある。どこにでも社会はある。そんな社会のなかでは日々さまざまな形の経済活動が行われている。だから稼ぎのある社会人でなければ社会に貢献できない、ということはない。あまりにも当たり前の話になるけれど、あらゆる人がその人なりの仕方で社会人である。そんな当たり前を「社会人」や「社会」という語の現代的な用法は覆い隠してしまっている。
ここで生活保護の話に戻れば、多くの人が生活保護を受給しない理由として、経済的な自由が制限されることのほかに、社会的な居場所がなくなることへのおそれも挙げられるのかもしれない。無職では何者でもなくなってしまう。社会的に孤立してしまう。そんな不安もよぎる。けれども、やはり、社会は思っているよりもずっと広いのではないか、と僕は思う。
生活保護を受ければ、さまざまな欠乏から自由でいられる。これは行動経済学者のダニエル・カーネマンという人が言っていることなのだけれど、金銭的、時間的な欠乏は、人を近視眼的にする。働かなければ生きていけないという強迫観念を抱えながら生きていると、それだけで生活に負荷がかかり、広い視野を持つことができなくなり、自分がはまりこんでいる穴から抜け出せなくなる。それが負のスパイラルを引き起こして悪化の一途をたどる。
いわゆるアテンション・エコノミーの全面化した現代において人は暇というものを持つことが難しくなった。「暇」という語が死後になりつつある気さえする。時間が経済的に最適化された世界はカーネマンのいう「余裕 slack」というものをどこまでも縮小させてしまう。そんななか、生活保護によっては必要以上の金銭を得ることはできないが、そのかわり「暇」を得ることができる。
その「暇」こそが本当はもっと広いはずの「社会」を発見する一助になるのではないだろうか。たとえば、時間的なゆとりができた分、地域の子供食堂で働いてみたり、移民の子供たちに日本語を教えてみたりすることができる。ある意味では、格差を拡大させつづける搾取の構造の歯車になって、終わりのない金稼ぎのゲームにあくせくするよりも、こちらのほうがずっと「社会的」であると言えるかもしれない。
ただ、生活保護を受給することで経済的な自由が制限されることは、多くの人の望むところではないだろう。また、一度生活保護を受けてしまうと、そこからなかなか抜け出しにくくなることも問題である。僕は今年の夏にフランスでの仕事に区切りがつき、さしあたりは日本で路上生活者をすることになったので、そのことについて、いろいろなことを考えたり試したいと思っている。この記事はその覚書ということになります。